前回の記事では僕の作品を作る制作環境について紹介しましたが、今回は僕の作詞について触れたいと思います。
昨今、AIクリエイターによる作詞作曲の作品が増えていたり、音楽性を優先する楽曲が多いのですが、だからこそ僕は歌詞や言葉にはこだわっています。
また、僕のアイデンティティという事もあり、基本的に作詞はAIに任せずに自分で作っています。
自分の言葉を紡ぐ(感情を切り取る)
インスピレーションの源
僕はいろんな場面で詩を綴りたいと思う思考の癖があります。
ブログとかを書いてアフィリエイトでもやろうと昔思って活動していた時期がありましたが、3ヶ月くらいしたらネタ切れを起こしたし、そもそも記事の作成が苦痛になって続いた事はないくらい駄目でした。ですが、詩だと全然そんな事が起きません。
何故かはわかりませんが、感情がちょっとでも動かされると、その瞬間を言葉で切り取りたくなるんですよね。
例えば些細な事ですが、今だと夏から秋に季節が変わろうとしていますが、この秋という季節は様々な感情を僕に想起させてくれます。
茹だる暑さだったのに、気持ちいい風が吹き込み、夕焼けの空がきれい。
肌寒く感じる時は人肌が恋しくなる。そういえばあの人は今何してるんだろう。
そういえばあの時は隣にあの人がいて、あの場所へ行った。
とか。
こんな感じの歌詞はもうすでに書いてますが、事実は1つだけでも、その表現を奥行きを変えたりしてまた綴りたくなるんです。
それ以外でも、ニュースをみて身勝手な人間の振る舞いに覚えた感情を言葉に変えたり、自分自身の無力さを感じたり、誰かを応援したいと思ったりと、毎日感情を忙しくさせています。
そうやって感情が動いて、文字で表現したいと思ったときに、その感じたことをメモにして残します。
熱いうちに叩かないと感情の鮮度が落ちるので、古すぎる内容のメモはそのまま没に成ることもありますが、それでもネタが尽きることはありません。
とにかく作品として表現したいと思った場面に出会ったり、過去の記録としてその瞬間を残したい時。他にも役立つ考えや、身近で伝え聞いた話や物語を言葉にして誰かに伝えたい時とにかく感じたまま言葉にしています。
詞を先に作るか?後か?
AIを使っているなら当然詞が先だろって感じもしますが、オリジナルで音楽作品をつくる人は圧倒的に詞の後入れが多いようです。
僕は詞の後入れが苦手で、AIを使っていない作品(Marbleで作っている作品)でも詞先か、詞とメロディの同時出しで作っています。
これは音楽的なメロディを主体にするのか?
詞の内容を主体にするのかの違いがあるのかなと僕は思います。
AIを使って作曲する場合、詞を先に作ってそれに合うように作曲してもらうという仕組みなので、詞先以外のプロセスは基本ありません(やろうと思えば後入れもできますが大変です)
もともと僕は趣味で「詩」を書いてきた人なので、メロディ先で後からいれる作詞は文字数制限があって苦手なんですよね。
職業プロ作詞家の方はそれでもうまいこと文字を整えたりするのでしょうけど、僕はメロディの為に表現したい文字を削るのが感覚的に嫌いです。
この点において、AIを使うと文字を削ること無く、詞を主体として音楽を簡単に変更できるので、これは間違いなくAIの強みだと思います。これを僕がAIを使うこと無くやろうとするとぎこちない音楽になったり、うまくハマらないとか問題が多数でてきますので。
「詩」と「詞」を使い分ける
僕の中で詩と詞は違いがあって、詩はメロディなどの制約なく作られる言葉で。詞はメロディなどの成約があるなかで音数に合わせて作られる言葉と思っています。
どっちにも良さがあると僕は思っていて、作品を作る時は意識してどちらかに寄せて歌詞を作ります。
つらつらと思った事を書き殴ったり、詩っぽく空白を作ったり、詞っぽく体裁を整えて書いていったりと、テーマによって変えます。
ここでAIによる作曲が生きてくるのですが、詩っぽく作った文字構成がバラバラな歌詞でも、AIはうまいこと調整して楽曲として成立させてくれるのです。もちろん何回が試行錯誤しないと、いい感じになったといえる作品はでてきませんが、それでも自分で作るよりはいろんな角度でたくさんの案を出してくれるAIは素晴らしいです。
当然音数を意識して作る詞は構成分けして、音数を意識して整えるのですが、このパターンで作ると今度は詩っぽく作った歌詞では出しにくいリズミックな、メロディックな楽曲を出してくれやすいです。
なので、テーマや作りたい雰囲気に合わせて詩と詞を使い分けて作っています。
AIはメンター。独りよがりな歌詞をどう変えるか?
独りよがりな歌詞を客観視する
kogkaの初期作品は書いた詞をそのまま曲にしていたのですが、最近は客観的視点で歌詞を見れるようにするため、歌詞が独りよがりになってないか?などをChatGPTやGeminiなどのAIに見てもらったりして、誤字脱字や文法的におかしくないかを含めてチェックします。
過去にChatGPTやGeminiに歌詞を作ってもらおうと考えたこともあり、色々試した事もありましたが、全然自分が良いって思える詩に出会えなかったので、歌詞を作ってもらうことはしていません。あくまでも自分で作ったものをブラッシュアップするためにチェックするという感じです。
ちなみにどういう感じでチェックしてもらうかですが、自分の中で明確に歌詞はこうありたいというビジョンがあります。最初からそれをクリアした作詞ができればいいのですが、徒然と書いた詞はその条件をクリアしていないことが結構ありまして・・・それに自分が気づくためにチェックしてもらって、ここで歌詞のブラッシュアップをしているという感じです。
チェックしてもらうとき、AIに適当に聞くと普通に褒めてくれる事が多いですが、聞き方を変えると辛辣に評価される事があります。傷つくレベルで。
僕がよく言われるのは、詞は聞き手に想像させる余白のある歌詞であることが大切だけど、説明くさい歌詞が多いと言われます(散文的であるとよく言われます)。僕が作る詞は抽象性のある表現が苦手で、現代のトレンドで比較するとよく酷評されます。
例えるなら平成時代の歌詞みたいな感じです。
仕方ないですよね。当時の影響が強いので。
でも最近思いますが、色々勉強していくなかで、歌詞が平坦で深くないなと思うようにもなってきましたし、言葉が浅いなと思うようにもなってきました。
とにかく、この評価を踏まえて、改めて自分が誰にどんな感じになってほしいか?という目的に照らし合わせて歌詞の内容を変えたり変えなかったりと分けて決めて作っています。
このブラッシュアップの工程でいろんなAIに聞いたり、修正を重ねるので最近は時間がかかるようになりました。
ちなみに、作品によって言いたい事が1テーマにならないようになってしまうケースがあるのですが、そうなったときは1作品にまとめるのが難しいので、アルバム構成にして、テーマに対して複数曲分の歌詞を作ります。
過去の言葉を『今の作品』に昇華させる
大筋こんな感じで作詞をしますが、僕は趣味で詩を書いていた作品が1000以上あるので、過去の詩を掘り返して作品にすることもあります。
ですが、過去作をそのまま発表するには青臭すぎて自分的にきついのが多いので、作品によって2割から8割修正して出したりしています。
修正・昇華のプロセス
修正する時は、その時作った詩の内容はだいたいシーンを覚えているので、その時の気持ちになって、今の視点から詩を作り変えます。
文章がとても拙く、「僕が」「あなたが」といった主語が頻出するときは、それを根こそぎ削ったり、詞の内容によって修正ポイントは様々ですが、今だしても大丈夫かなと思うようなレベルにして変更しています。
中にはわざとそのままの稚拙さで出すものもあります。
このような流れで歌詞を95%程完成させ、次に作曲AIでの作業に移ります。
残り5%はその作曲AIでどうしてもうまくいかなかった時、メロディにのせて違うなと感じたときに修正します。
終わりに
ざっと自分の詞の作り方について書いてみました。次は作曲編について触れたいと思いますが、この記事を読んでもらって、詩について興味を持ってもらえると嬉しいです。
僕のオススメはまずは日記のように、感情を言葉にしてみる事です。
心のなかにモヤモヤしている何かがあれば、それを言葉にするだけでスッキリするし、意外といいものです。
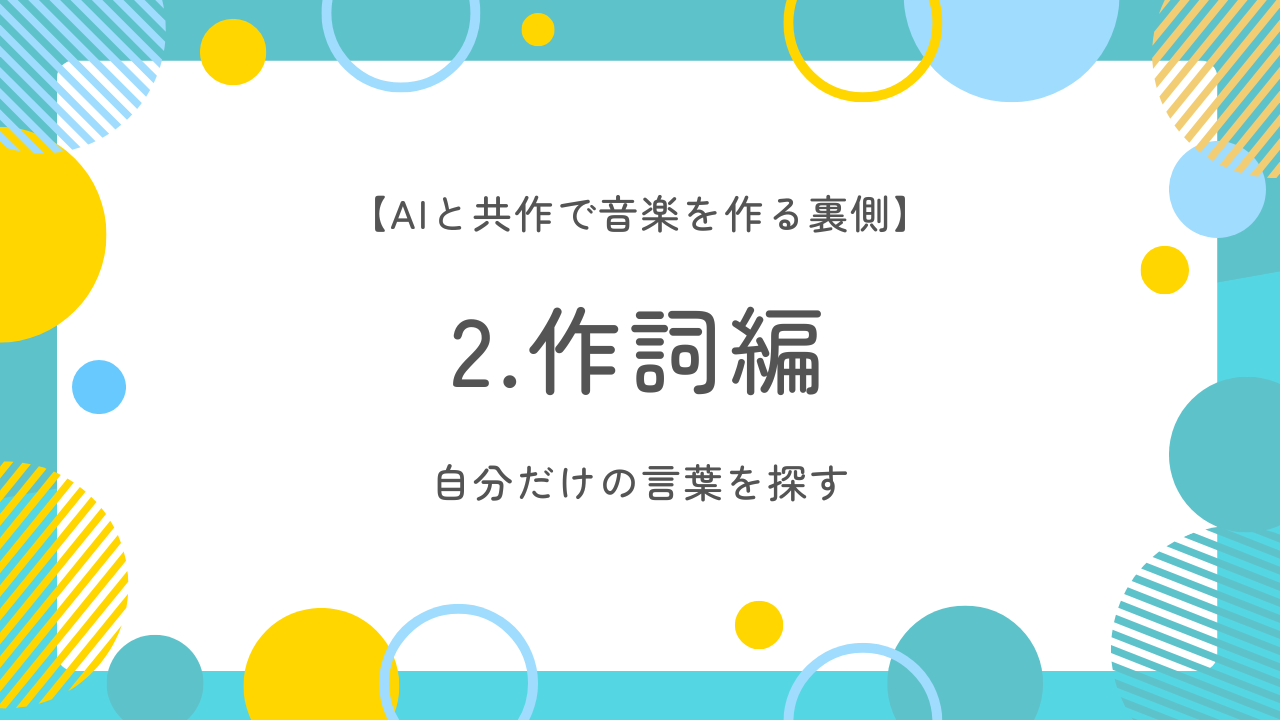
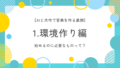

コメント